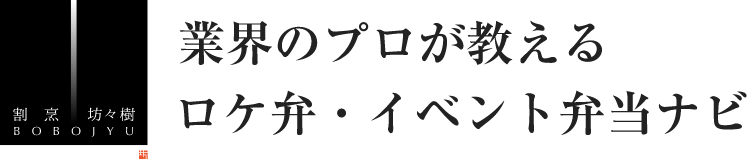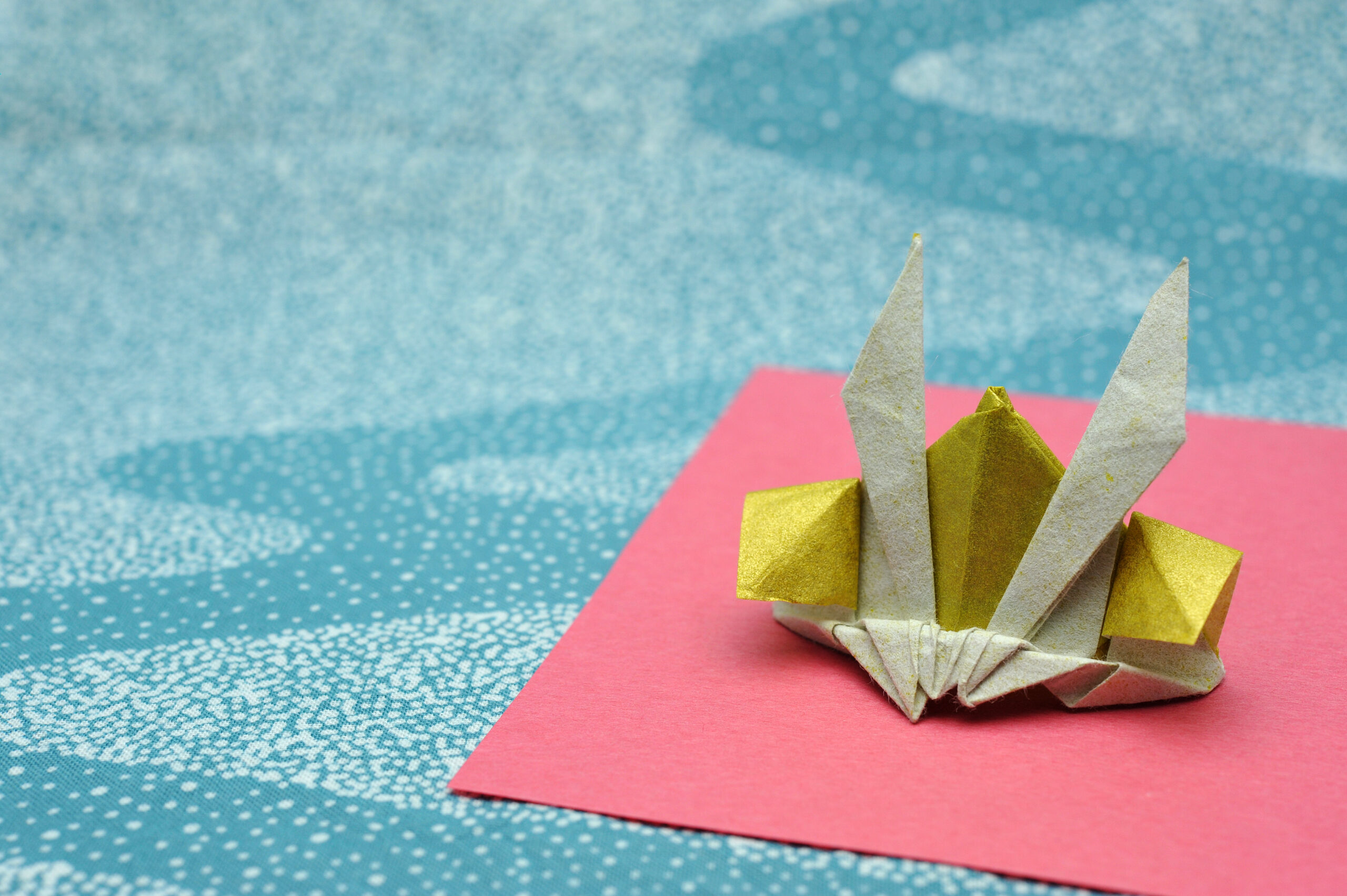5月5日は端午の節句です。3月3日は桃の節句で女の子がメインとなりますが、5月5日は男の子がメイン。端午の節句にちなんだ料理を食べるご家庭も多いのではないでしょうか。
今回ご紹介するのは端午の節句で食べる料理の種類や意味、そもそも端午の節句の由来とは何なのかです。意味を知って楽しむ端午の節句はまた格別です。
端午の節句の由来

端午の節句は桃の節句と同じく、中国の風習が由来とされています。当時の中国は奇数がゾロ目で揃う日、例えば、3月3日、5月5日、7月7日などを嫌っており、お祓いを行うのが一般的でした。
日本でもこの風習が取り入れられ、5月5日は当初菖蒲の節句と呼ばれました。これは中国において菖蒲をお祓いに使っていたことが理由とされています。その後、菖蒲の言葉の音から武士を連想し、現在の五月人形が登場するなど、男の子を祝う日になっていきます。
端午の節句で食べる料理 行事食編

端午の節句ではいくつか代表的な料理があります。最初にご紹介するのは端午の節句だからこそ食べられる行事食です。行事食の由来と意味についてご紹介していきます。
ちまきの由来と意味
ちまきは漢字で書くと「茅巻き」ですが、これはもち米などで作ったお餅のようなものを茅の葉で巻いたことから言われています。
ちまきは中国で食べられていましたが、昔、忠誠心の高い政治家が川に身を投げてしまう出来事が起きました。それが5月5日でした。当時の人たちはこの死を悲しみ、5月5日にちまきを投げて供養を行っていました。忠誠心の高い大人になってほしいという願いも込められており、この風習が日本に伝わり、ちまきを食べる文化につながったのです。
柏餅の由来と意味

柏餅はちまきと同じ餅系ですが、柏餅は日本で誕生した風習です。柏餅が生まれたのは江戸時代で、柏餅を巻くカシワは新しい芽が出るまでは葉っぱが落ちない特性があり、これに目を付けた人たちが、家が途絶えないという意味を持たせたことがきっかけです。
一方でカシワ自体が関東中心にしか生息しておらず、西日本では普及しない代わりに、別の葉で包むこともありました。のちにカシワの葉が海外から入ってくるようになったことで全国的な広まりを見せるようになります。
端午の節句で食べる料理 お祝い編

端午の節句はお祝いなので、お祝いの日だからこそ食べる料理もあります。ここでは端午の節句で食べるお祝いの料理についてご紹介します。
タケノコ料理

タケノコは5月が一番の旬とされ、おいしいタケノコがこの時期に出回ります。旬だから食べるという意味合いもありますが、そもそもタケノコは生命力があり、真っすぐに上に向かって育つ性質が特徴的です。
自分の息子もタケノコと同じように育ってほしいという意味が込められ、様々な料理に応用され、出されます。
カツオ
カツオもまたタケノコと同じく、5月あたりが旬の魚です。今でこそカツオは安く手に入りますが、当時は高級魚でなかなか食べる機会はありませんでした。そのカツオは本来鰹と書きますが、「勝男」と書くこともできるため、縁起のいいものとして出されます。
何と言ってもカツオは刺身で食べるのが一番ですが、煮物にするケース、カツオのたたきで食べるケースなど地域によって様々です。
ブリ
ブリは皆さんご存じの出世魚です。大きくなれば名前が変わっていくことから、端午の節句を祝うにはうってつけの食材です。刺身で食べることもできますが、ブリの照り焼き、ブリ大根とバリエーションも豊富。
近年はブリの刺身をしゃぶしゃぶにして食べる、「ブリしゃぶ」も人気です。ヘルシーにサッと食べられるブリは今の時代に適した食材であり、端午の節句を祝うのにもぴったりです。
まとめ
本記事では、端午の節句で食べる料理の種類や意味、そもそも端午の節句の由来とは何なのかについてご紹介しました。意味を知った上で端午の節句を楽しむのとそうでは無いのとでは、また違った形で楽しむ事ができます。今年の5月5日はイベントの意味を理解して楽しむのも良いかもしれません。